ダニエル・キイス著/小尾芙佐訳/早川書房
 帯にもあるとおり、トレンディドラマ枠で、この小説のテレビ番組が始まりました。
帯にもあるとおり、トレンディドラマ枠で、この小説のテレビ番組が始まりました。
実際のところ、私にはほとんどこの小説を気にしたこともなかったのですが、どんなところにも、「感動の名作!」と書かれており、最近急に気にしだしたのです。
テレビ番組で最初に見たとき、手術によって精薄者が天才になるというようなストーリーだということがわかり、これってうまく描いてあるのなら、私的にも非常に面白いと思える内容なんじゃないかなと思い始めました。
文庫本の裏にある小説の紹介では、こんな風に書かれています。
「超知能を手に入れた青年の愛と憎しみ、喜びと孤独を通して人間の心の真実に迫り、全世界が涙した現代の聖書」
現代の聖書とは大きくでたなあ、と思いましたが、確かにこの紹介文に違わない、実に実に感動的な小説でした。マジに泣けました!
簡単にストーリーを紹介しましょう。
32歳になっても幼児程度の知能しかない、いわゆる精神薄弱者であるチャーリー・ゴードンは頭が良くなる手術を受けます。とはいえ、この手法はまだ実験段階であり、チャーリーはいわば始めての人体による実験となったわけです。
この手術により、チャーリーは次第に頭が良くなります。ついには、この手術をした教授たちを凌駕する知能を手に入れますが、チャーリー自身の研究によりこの効果は一過性しかなく、またもとの知能に戻っていくことを自ら発見します。そして、最後には知能がついに元に戻っていってしまうのです。ちなみにアルジャーノンとは、同じ手術を受けたネズミの名前で、チャーリーがこの効果に永続性がないことを知るきっかけを与えています。
この小説はチャーリーによる、自身の身の上に起こることの経過報告、という形で書かれています。いわゆる日記風小説なわけです。物語の冒頭と最後は、日本語訳ではほとんど漢字がなく、句読点もない、幼児風の文体となっています。そして、この文章表現を見るだけで、チャーリーが次第に頭が良くなる様子、あるいは元に戻っていってしまう様子が的確にわかるのです。
まず、この基本的なアイデアそのものが、非常に面白いと思いました。そして、この小説の感動は、この構造なしに語れないものです。
さて、はっきり言ってしまえば、この小説における感動とは非常にヒューマニズムに根ざしたものです。確かに全体的なアイデアはSF的とも言えますが、著者は徹底して人間の精神活動を分析し、この架空な設定の中にも各人物の行動にリアリティを与えることに成功しています。
何人かの(いろいろな意味で)魅力的な人間が現れます。
まず何といっても、この小説に感動を添える大きな役割を果たしているのは、チャーリーが通っている精薄者の学校で教えているアリス。チャーリーは知能を得るに従い、このアリスに好意を寄せるようになります。アリスもチャーリーを愛しますが、この二人の愛はチャーリーの目まぐるしく変わる知性に翻弄されます。特に終わりのほうでチャーリーが元に戻っていくときの彼女の献身がどうにもいたたまれなくて、これが涙を誘わずにいられないのです。
チャーリーの母親も重要な人物だと思います。自己中心的な発想でしかものを考えられない、精神的に未熟な母親が実にリアルに描かれています。チャーリーは頭が良くなるにつれ、昔の母親の記憶をどんどん思い出します。妹が生まれるまで、精薄者であるチャーリーを無理やりにでも正常にしようと頑張る様子。ところが、妹が正常な人間として生まれると今度はチャーリーが疎ましく思えるようになり、自分たち家族の幸せを阻害するものとして敵視し始め、ついに自分の家から追い出してしまいます。父親は終始一貫してあるがままのチャーリーを受け入れようと説得しますが、ほとんど狂気じみた振る舞いでチャーリーを追い出してしまいます。そして、チャーリーはそのときのことも克明に思い出すのです。
しかし、その母親をチャーリーが頭が良くなってから訪ねたとき、彼女はすでにまともな精神状態の人間ではありませんでした。この事実がまた、私たちの心を締め付けます。ヒステリックで思い込みが激しく未熟な精神の持ち主の末路とでも言うのか・・・彼女はまた精薄者の息子を持つという精神的な重荷に絶えられなかった被害者でもありました。
それほど重要でないが、やはり感動を誘った人物として、ギンペイがいます。彼はチャーリーとともにパン屋で働いていた従業員です。手術を受けたあと頭が良くなったチャーリーはギンペイが不正に値引きをして、その差額を客と分け合っている事実に気がつきます。チャーリーはその不正を見過ごすことが出来ません。そして、ギンペイにそのことを注意するのです。それまで白痴同様だったチャーリーが急に頭が良くなって、ついに自分の不正を問いただすなどということをされたギンペイは、もうすでにチャーリーはただの嫌なやつにしか思えなくなってきます。
ところが、物語の最後の最後、知性が元に戻ってしまい、パン屋に舞い戻ってきたチャーリーがいじめられて、それをギンペイが助けてやるところなど、やはりほろりとさせられます。
なんだか、こう書いていると細かいことばかり書いているような気がします。
ただ、実際のところ、一般に言われているように、頭が良くなることが本当に幸せなことだろうか、というような単純な問いかけだけで出来ている小説ではないと私は言いたいのです。確かに頭が良くなるにつれ、周りの人々の愚かさに気付き、それゆえに孤独になっていく様は非常にうまく描かれていると感じました。
しかし、恐らくもっと根深い問題として、知性と、その知性をうまく扱うだけの精神的な成長とのアンバランスさもうまく表現しているように思うのです。実際のところ、この手術の効果はあくまで知能面だけであり、その知能の成熟と衰退の時期が、精神的な成熟と衰退と微妙にずれているところが、この小説の構成のうまさだとも感じます。
SFの設定として若干無理があるのを感じるのは、頭が良くなっていって20ヶ国語を扱えるようになるだとか、ピアノ協奏曲を作曲するだとか、その他様々な理論を習得してしまい専門家の無知をさらけ出してしまうとか、割と天才について過激な描写をしているところです。まあ、そのあたりは物語の本筋とは関係ないし、一般の人々が天才だと思うようなことを半ば俗っぽく表現してあげたということなのかもしれません。
この小説は1966年に発表されており(私の生まれた年!)、すでに古典の領域に入るくらい有名なものらしいのです。それにしては、よく今まで私のアンテナに引っかからなかったなあ、と思います。
SF好きでなくても、ヒューマンもの好きでなくても、この小説の持つ根源的なテーマは多くの人を感動させることは確かなようです。
スピルバーグものは前回A.I.も見に行ったのですが、なかなか世の中のスピルバーグを見る目は厳しいようで、今回もこの映画、いろいろな批評ではあんまり良く書かれていないようです。
私もそれほど期待していなかったので、見ようかどうか迷っていたのですが、お正月でちょっと暇もあったので見てみることにしました。
それで結論から言うと、私的には結構面白かったです。
私の場合、SFのしかも近未来に起こりうる特殊なシチュエーションもの、というタイプの映画が好きなようです。
この映画の特殊シチュエーションとは、犯罪を事前に防ぐための予知システムがあったら、というもの。予知能力のある人間を半ば道具のように使って、その犯罪を未然に防ぐというのは、一見荒唐無稽のようでそれなりにディテールのある設定だと思いました。問題は、犯罪を予知してそれを事前にやめさせる、ということは、結局その犯罪は起こらなかったことになるわけで、では一体何を予知したことになるのか、そういうパラドックスを感じないではありません。
ただ、この設定には文明のある側面を痛烈に皮肉った部分があり、それゆえにこうした特殊設定は面白いと思うのです。
人々は誰も犯罪のない平和な世の中を欲しています。犯罪がないということは、犯罪者がいないということ。犯罪を起こしそうな人がいれば、それを未然に防いでしまえば、当然犯罪は起きなくなります。
しかし、犯罪を起こす前の人はそもそも犯罪者と言えるのか、という素朴な疑問が起きます。そのように未然に解決されてしまった事件は果たして本当に起きるべくして起きた事件と言えるのか。あるいは事件は、そのシステムを逆手に取ることによって逆に操作することが出来たりしないか。そして、まさにこの物語は、そういったシステムの矛盾をあぶりだすことが目的になっているように思えます。
主人公アンダートンは、この犯罪予防局の捜査官。彼は、自分自身が殺人を犯す予知を見てしまいます。殺す相手は全く見たこともない人間。誰かが罠を仕掛けたと思い、逃亡しながらも新事実を掴もうとする、というのが大まかなあらすじ。
いささか筋が複雑で、特に後半に様々などんでん返しが起こり、そのたびに映画を見ている人を混乱させます。この映画、かなり注意深く見ていないと、大切な伏線を見落としてしまいそうになります。そのくせ、2時間半という時間は割と長い部類に入りますから、見ているほうは結構疲れるかもしれません。
実際のところ、真犯人の使う方法は映画で表現するにはいささか複雑すぎたのではないか、という気がしないでもありません。それが解決するのが最後の最後で、それまで映画内の様々な情報を記憶しておくのはちょっと大変。
それでもこの映画が、単なるドタバタなアクションものに終わらなかったのは、最後に「なるほどね」と思わせるということ。もっとも映画じたいはあんまりアクションものを指向しておらず、派手なアクションシーンはむしろ前半に集中しています。逆に言えば、筋が複雑だったからこそ、最後のなるほど感が強まり、気持ちよく映画を見終えたのかもしれません。
そういう意味では、ストーリーそのもの、謎そのものが奥深く、面白い映画だとも言えます。
また、近未来の描き方もなかなか良かったように思います。50年後ならあり得そうな数々のアイテムは、技術者としても十分楽しめるものでした。人が空を飛ぶのはそう簡単ではないと思いますが、セキュリティ関係、表示装置あたりは、50年も経たないうちに実現するかもしれません。
私が個人的にスピルバーグものの一つの欠点に思えるのは、全てをヒューマニックに解決しようとしてしまうこと。良くも悪くも勧善懲悪的なアメリカ映画の枠を超えられないということです。
例えば予知に使われていた3人の少年少女が、システムが崩壊した後、3人幸せに暮らしましたとさ、というのはあまりに人が良すぎませんか。
それから、本来シリアスなアクションシーンが、わざとドタバタ的な面白さにしようとしているところも、いかにもという感じ。アンダートンを捕まえるために、小型の探索機がボロアパートを探索するところも、そんな要素があります。スピルバーグには、恐らくシリアスになってしまうアクションシーンが耐えられずに、こういったささやかなジョーク的要素を入れてしまうところがあるような気がします。それは、SF作品を作るにはいささか優しすぎる態度です。
まあ何はともかく、この映画、設定の面白さ、謎解きの複雑さ、というのがポイントでしょう。
できれば、少しだけ筋を省略して、もう少しこのシステムの根源的な問題点、すなわち事件を起こす前に犯人を逮捕してしまうという危うさが表現されていれば、もっと含蓄のある深い映画になったような気がします。
安部公房著/中公文庫
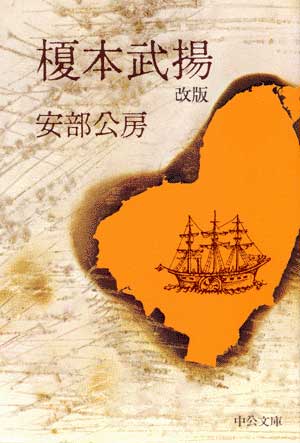 先日、NHKの番組で「その時歴史は動いた」で、榎本武揚をやっていたので、つらつらと見ていたのですが、恥ずかしながらこのときある事実を私は初めて知ったのでした。
先日、NHKの番組で「その時歴史は動いた」で、榎本武揚をやっていたので、つらつらと見ていたのですが、恥ずかしながらこのときある事実を私は初めて知ったのでした。
正直に言うと、私は榎本武揚が五稜郭の戦いで戦死、あるいは自害したものとばかり思っていたのです。ところが、何とこの人、降伏して捕われの身になったばかりか(それだけなら驚きはしないが)、出所したあと明治新政府で出世街道まっしぐら。ついには、逓信大臣、文部大臣、外務大臣などを歴任する大政治家になってしまったというではないですか!!!
しかし、明治維新といえば、これは歴史的には革命みたいなもので、幕府軍と薩長軍が戦争を開始してからの一連の戊辰戦争の中で、五稜郭の戦いは最後の戦いです。その革命のさなか、旧体制を代表する、しかも最後の戦いの中心人物が、降伏後処刑もされず罪を免れたことがまず信じられません。
それから出所後、明治新政府に勤め、ついには大臣になる?そんな馬鹿な・・・恐らく世界の歴史の中でも、これは全く稀有な出来事といえるのではないでしょうか。仮にこの事実を、もっと昔に私が知ったとしても、同じように考えたと思います。
この何か釈然としない歴史的事実にまさにスポットを当てたのがこの小説。
実は、この本、BOOK OFFで買った古本。
割と安部公房が好きな私が、本屋でこの本を目にしたとき、「エっ」と思ったのです。だって、短編中心の、ちょっとSFっぽい、実験的な作風のあの安部公房が歴史小説!?しかも題名だけでは、人物に焦点を当てた大河小説的な感じさえします。
それで、そのときはつい興味が湧いたのと、値段も安かったので衝動的に買ったのですが、実は何となく読むきっかけを失ったまま、今まで私の本棚に埋もれていたのでした。
それで、前述の衝撃の事実(知らなかった私が恥ずかしいんですが^^;)。
早速、安部公房のこの本のことを思い出して、読み始めてみたんです。
で、結論から言うと、これは歴史小説ではありません(キッパリ)。ましてや、榎本武揚の生涯を綴った伝記小説でもありません。安部公房節は健在で、内容そのものが、ある人から送られた手紙と資料という体裁を取っているので、途中で新聞の切り抜き記事が載っていたり、漢文の詩が出てきたり(理解不能でしたが・・・)、手紙の内容だったり、手紙を受けた人の注釈だったり、と様々な文章がコラージュ風に配置されているのです。
安部公房といえば、カフカを思わせるような不条理系の文学と私は思っているのですが、恐らく安部公房も、私が最初に感じたように榎本武揚の生き様をまさに不条理だと捉えたのではないかと感じます。だからこそ、氏の小説の題材として選ばれたのではないでしょうか。
そして、安部公房はこの不条理さの結論を、五稜郭の戦いは八百長戦争だった、とします。つまり、榎本武揚は明治への時代の流れを進めるため、敢えて反政府軍の指揮を取り、しかも最後には負けるように事を運んだというのです。最後にもう全く勝ち目がなくなったとわかったとき、榎本は自害を企てます。しかし、それも側近が控えていて、必ず自分の自害を阻止するという確信があったこその芝居だった、というのです。
歴史的に見れば、こんな結論の方が荒唐無稽なのは確かですが、不条理に理屈を通すともっと不条理な結論が浮かび上がるという安部公房的な流れに思わず納得感。しかし、榎本武揚という底知れぬ知性が秘める力なら、こんなにうまく事を運ぶことも可能なのかもしれない、と考えてしまいます。
榎本武揚のその不思議な生涯に、思わず立ち止まり考え込む人は多いと思います。その変節ぶりにはあまり触れられませんが、例えば北海道共和国がもし成功していればどんなになっていたか、などと空想を膨らます人も多いのではないでしょうか。
感情的に彼の行動を納得もって理解できない不思議な人物、榎本武揚。そしてまた彼は近代日本の知性を象徴する人物です。いつまでも、彼のそのあやしい魅力は一定の人々を惹きつけて止まないのかもしれません。
椎名林檎
 また買ってしまいました。椎名林檎。
また買ってしまいました。椎名林檎。
しかしなあ、このタイトルは・・・。意味不明だけど、怪しさだけは十分伝わる。でも、このタイトルだけで買うのをやめてしまった人もいるのでは、と推察します。
で、本当は、一度「面白かったもの」で取り上げたので、このCDもわざわざ書くつもりなんてなかったんです。本当に音楽を聴くまでは・・・。
そういうわけで、今回のこのアルバムは、相当ブッ飛んでいます。いや、そういうと誤解を受けるかもしれません、特に椎名林檎の場合。
前回アルバムのストレートな破壊的歌唱の世界とは違うのです。もう、巻き舌も出てきません。何がブッ飛んだかというと、サウンドなのです。これは、もはやバンドの音ではありません。完全にマニアックな多重録音の世界で、これでもかというくらい、録音技術をアーティスティックに駆使しています。
制作費を心配してしまうくらい、多彩な楽器が、ほんの一フレーズのために現れます。「生ハープシコード」とか「生パイプオルガン」と書いてあるけど、ホントに生を使ったんでしょうか。宅録に徹するなら、電子楽器でもいいと思うんですが。別に生の臨場感が欲しくて使っているようにも思えないし。
もちろん、多重録音の世界といっても、一頃のような打ち込みサウンドとか、コンピュータのピコピコサウンドではありません。むしろ、その逆で、華麗なオーケストレーションによる派手なサウンドだったり、ワイルドなベースとリズムによる曲だったり、そういう全く方向性の違う録音の曲が一つのアルバムの中に混在しているのです。
様々なタイプの曲と言いましたが、実はこれらの曲は必ず2曲セットになっていて、第6曲「茎」を中心にシンメトリに配置されています。1曲目と11曲目、2曲目と10曲目・・・、というように類似した編成(と曲名も)の曲がセットになっているわけです。これって、例えばクラシックならバッハが良く使う方法。ロ短調ミサのCredo、ヨハネ受難曲の第2部とかが、そんなシンメトリ構成になっています。
こういった妙に知的な作業が、破壊的な表現と表裏一体となっているのが、私にとっての椎名林檎の魅力です。今回のアルバムでは彼女自身の初のセルフプロデュースであり、なんと一部オーケストラアレンジもやったり、鍵盤系楽器も彼女が弾いています。マニアックな音楽家としての側面が、椎名林檎にはあります。
結果的にこのアルバムは、プログレと言える域に達しています。ただし、まだ楽曲の基本構成は、ポッポスの枠をそう外れるものではありません。もし、曲が複雑な構成だったり、変拍子を使ったり、テンポを揺らし始めたりすると、もう完全にプログレですが、それを期待してしまうのは、まあ私くらいのもんでしょう。
実際のところ、このアルバムで椎名林檎はもう売れ線を放棄しているとさえ、感じました。このサウンドでは、いわゆる普通のJ-POP好きはもうついて来てくれないのではないでしょうか。しかも、これまでのバンドサウンドを好んでいた人ならなおさら。
セルフプロデュースで、好きなことを自由にやってしまったがために、マイノリティになる方向を選び始めたのかなとも思ってしまいます。ただし、J-POPのアーティストが数年で消費されてしまう昨今、その流れに決して飲み込まれない芯の強い音楽的信念をなんだか感じたようでとても頼もしく感じました。
さて、その大きな特徴とも言える椎名林檎の詩の世界ですが、シュール度をさらに高めました。ほぼ、全曲がシュール系、ナンセンス詩と化しています。いや、もうちょっと正確に言えば、シュール系、内容はっきり系が、だんだんブレンドされて、注意深く読まないと内容が見えてこないようになりました。ただし、言葉の使い方などの表現方法は彼女なりに優しくなってきたような気がします。
もう一つ、その方向性を助長するように、音楽の中で歌がかなり引っ込んでミックスされています。恐らく、ほとんどの人が、「えっ、歌が聞こえない」と思うでしょう。言葉の配列がシュールなので、次の言葉の予測が出来ず、音楽を聴くだけでは歌詞がわからないという事態が発生しています。
歌の基本は、歌詞をしっかりと聞かせるということにあるわけですが、これに椎名林檎は背を向けています。それが、サウンド指向、音楽指向の彼女の方向性を裏付けているようにも感じます。そして、その不足分を補うために、タイトルを過激にしたり、旧仮名遣いにしたり、見せ方を工夫しているのではないでしょうか。
もちろん、今後の椎名林檎の方向性がずっと同じようになるかはわかりませんが、ある種の音楽へのこだわりをこのアルバムで表明したことにより、10年、20年後にどのような活動をしているのか、ちょっとだけ想像できるようになった気がします。
TRY-TONE/Pony Canyon PCCA-01868
 談話などで取り上げることも多かったトライトーンですが、最近発売されたこのCDが結構良かったので、こちらでも紹介します。
談話などで取り上げることも多かったトライトーンですが、最近発売されたこのCDが結構良かったので、こちらでも紹介します。
近年ハモネプなどと称して、アカペラが流行りだしたのは、なんだかんだ言ってこういったジャンルに注目が集まって良かったことだと思います。
そして、日本のアカペラバンドの中でも、実力面でピカ一なのがこのトライトーン。もちろん、ハモネプ出身でもなかなかやるなあ、と思うバンドも最近は出ていますが、基本的にトライトーンの場合売り方のテーストが違うのです。
アカペラバンドと言っても、これまでのロックバンドと同じような売り方をしようと思えば、やはり曲はオリジナルになるし、シンプルなラブソングになってしまうものです。
もちろんオリジナルソングは大事だけど、アカペラの面白さを味わうためにはどうしても技巧的な側面は必要で、既存の曲をアカペラ用の面白いアレンジで聞くというのは大事な方向性だと私は思います。
トライトーンの場合、オリジナル度を抑えて、様々なコンセプトで曲を集め、オリジナルアレンジでアカペラを聞かせるというのが基本的スタンス。メンバーはそれほど年齢が高いわけではないけど、音楽的には若者よりも大人のリスナーをターゲットにしているように思います。
そして、今回のコンセプトは日本の唱歌。
絶対昨今のアカペラバンドならこんなCD出しません。しかし、誰もが知っている曲というのがこの選曲の最大の強みで、よく考えたら老若男女誰もが楽しめるんじゃないかと私は思います。
そして、またこの良く知られた曲をトライトーンがどのように料理したかというのもこのアルバムの最大の聞きどころです。
外国曲ならジャズフレイバーのアレンジでも、原曲とそれほど変わらない感じを受けますが、何といっても日本の唱歌ですから、かなり原曲のイメージと異なることが予想されるわけです。
そして、結果的には一昔前の日本の叙情を湛えながら、シャープな音楽的表現も持ったかなり濃いアルバムになっています。ただし、曲数が多いのと、どうしてもアップテンポに見合う曲が少なくなり、ちょっと全体的にヒーリングっぽい雰囲気を醸し出しています。また今回は日本臭さを抜くためか、アレンジも素直でないものが多く、抽象的な音使いが多くなってきました。かなり渋くて、一般のリスナーがついてこれるかちょっと心配。
音楽的なアレンジの面白さとしては、例えば「春のうたメドレー」などで複数の曲を同時に歌ったり、他の曲などでもポリフォニックなアレンジが随所に見られるようになりました。「朧月夜」「椰子の実」の幻想的な雰囲気も心地よい。「村祭り」では4度ハモリがかなりエキセントリックな雰囲気を醸し出します。「ちいさい秋みつけた」では、拍子をいじって耳を引き付け、ボサノバっぽい雰囲気が気持ちよく聞けます。「ペイチカ」では思い切った二声アレンジが聞けます。
そして一番面白いアレンジは「待ちぼうけ」。これ、初期の矢野顕子っぽいですね。何か70年代のプログレの匂いがします。曲調が頻繁に転換するのでライブで聞いても面白そうです。
こういうアルバムを聞くと、無性に自分でもやりたくなります。
アレンジなら、私はいくらでも面白いモノを作る気合はあるんですけど、残念ながら歌のほうが追いつかないです。(T_T)
トライトーンの5人はみんな本当に歌がうまいのです。歌がうまいと、一言では言うのは簡単だけど、歌のうまさにはいろいろな要素があって、アカペラにおいてはその全てが要求されるのです。
音楽の最も基本でありながら、声楽ではあまり省みられないソルフェージュ力は、アカペラの場合その実力差が露骨に表れます。それから、やはり歌ですから基本的に声の良さ、大きさ(何度も言っていますが、声の大きさはその人の表現力のキャパシティのためにある程度必要なものです)も必要。「ペイチカ」の二声アカペラなど、声の良さ、歌の表現力がなければ、聞けるものにはならないでしょう。
そして、あと重要なのは練習!同じメンバーでずっとプロ活動をしていれば、練習はどんどん効率的になってくるでしょう。プロだからこそ、さらにうまくなっていく可能性があります。息のあわせ方、裏拍の突っ込み加減、クレシェンドのかけかた、間合いの取り方、こういったアンサンブルの細かい加減がアイコンタクトだけで出来るようになれば、さらに深い音楽表現にもトライしていきたくなるというもの。
彼らの音楽的能力を羨ましいと思う反面、トライトーンは今のアカペラブームの中でもっともっと広く知られて欲しいと思う実力派バンドです。このアルバム、かなりお薦めです。是非聞いてみてください。
◇戻る◇

 帯にもあるとおり、トレンディドラマ枠で、この小説のテレビ番組が始まりました。
帯にもあるとおり、トレンディドラマ枠で、この小説のテレビ番組が始まりました。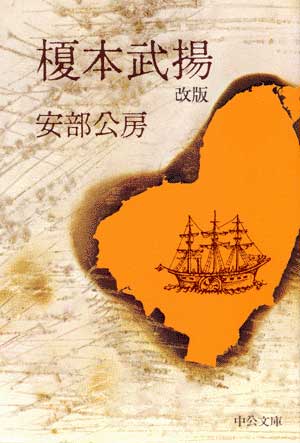 先日、NHKの番組で「その時歴史は動いた」で、榎本武揚をやっていたので、つらつらと見ていたのですが、恥ずかしながらこのときある事実を私は初めて知ったのでした。
先日、NHKの番組で「その時歴史は動いた」で、榎本武揚をやっていたので、つらつらと見ていたのですが、恥ずかしながらこのときある事実を私は初めて知ったのでした。 また買ってしまいました。椎名林檎。
また買ってしまいました。椎名林檎。 談話などで取り上げることも多かったトライトーンですが、最近発売されたこのCDが結構良かったので、こちらでも紹介します。
談話などで取り上げることも多かったトライトーンですが、最近発売されたこのCDが結構良かったので、こちらでも紹介します。