中根千枝著/講談社現代新書
 談話などで日本人について論ずることが良くあります。多分、私の中でかなり興味あることなのでしょう。それで本屋に行っても、ついついその手の本を手にとってしまうのです。たいていは人生指南書的なものがほとんどで、内容的にはたいしたものがないのが常です。そうした本を見るにつけ、もっと学術的に日本社会を論じたものはないのか、という気持ちが私の中で感じていたところでした。
談話などで日本人について論ずることが良くあります。多分、私の中でかなり興味あることなのでしょう。それで本屋に行っても、ついついその手の本を手にとってしまうのです。たいていは人生指南書的なものがほとんどで、内容的にはたいしたものがないのが常です。そうした本を見るにつけ、もっと学術的に日本社会を論じたものはないのか、という気持ちが私の中で感じていたところでした。
さて、この本「タテ社会の人間関係」は、まさにそういった学術的な観点から日本人を論じたもので、この手の日本人論の古典的名著と呼ばれている本なのです。これを読まなきゃモグリというほどのものらしく、今までこの本を知らなかったことを全く恥じるばかりです。ちなみにこの本が最初に世に出たのが1967年。その反響の大きさからその数年後には英訳版、仏訳版も出され、日本人を知ろうとする外国人にもすでに広く読まれている超ロングセラー本です。
学術的といっても難解な言葉で書かれているわけでなく、非常にわかりやすく、時にあえて俗っぽく書かれており、一般書として十分読める文章です。また、図解も多く、なぜかa,b,X,Yとか表現することが多く、ぱっと見ると数学書と思える部分もあり、もしかしたら結構理系的な本かもしれません。
さて、この本の具体的な内容ですが、なにしろ目から鱗の連続で、私がこれまで断片的に感じていたことが体系的に述べられており、まさに座右の書と呼べる本であったといえるでしょう。著者自身がそのような日本的社会に疑問を感じているのが明白で、自らは学術書といいながら、なかば自虐的に日本人を論じているあたり著者の気持ちがとても出ていて、面白く感じました。
この本の中ではいくつかのキーワードがあります。
一例を挙げますと、集団構成の原理として「資格」「場」の二つがあるということ。「資格」による集団とはその人が持つ能力や資質の共通性によるものであり、「場」による集団とは一定の場所、共通の機関など同じ場所を共有しているものを指します。そして日本は、「場」による集団意識が非常に強いのが特徴なのです。著者によると、最も対極的なのがインドで、こちらは極端に「資格」に重点が置かれています(カーストが象徴的)。中国や欧米はどちらかというとインドよりですが、それほど極端ではありません。
そして、そのように「場」の共有が中心になると、「資格」の違いがあるものを一つの集団に抱え込むことになります。もともと「資格」の違いは人間的な性向や能力の違いであり、そのような異質の人間をたくさん内包することにより、その集団結集力をより強力にする必要が出てきます。そして、それは「そのグループの成員である」というエモーショナルなアプローチによることが非常に多くなるのです。これは何を意味するかというと、絶えざる人間同士の接触が必要ということであり、この傾向が強くなるにつれ個人は生活のほとんどをその集団に捧げる結果になります。
そのように生活の多くの部分において集団に関わるようになると、自然と公的なものと私的なものの区別がつかなくなります。会社を離れても仕事がついて回ったり、逆に会社の中でも私的な楽しみがあったりするのは誰でも心当たりがあるでしょう。また、他の社会に比べても極端に社内結婚や同じ村内での結婚が多いことを著者は指摘しています。
この話だけでも、論理的に集団を論じているのがおわかりになりますでしょうか。
この他、日本的集団の排他性、それに伴う個人の非社交性、それから集団内の序列(集団に関わる期間の長さに比例-私が談話などで書きましたね)、人間平等主義、日本的リーダーのありかた(頭が切れるより、部下を盛り立てる力が必要)、契約精神の不在、などが論じられています。
いずれも著者は、ささいなところで発見できる日本人的な部分を紹介し、それが国際的な場でいかに奇異にうつるかを描いています。著者自身が、そういうことを自分の活動の中で強く感じていることの現われでしょう。それから、著者が女性である、ということはこの本の成立に大きく関わっているのではないか、と私には感じます。もし、この本を男性が書いたのなら、その人は集団内の自分の地位が危なくなるんじゃないでしょうか。学問の世界でさえ日本的社会は浸透しているわけで、まだまだ仕事場では男性社会が中心だった当時だからこそ、女性の手で始めてその現状を糾弾することができたと思えるのです(学術調査団内の人間関係など思わず納得)。
ところで、この本を読んで、今まで自分が感じていたことをうまく表現されていることの快感以上に、日本人に対するある種の救いのなさに襲われたのは事実です。先に言ったように、この本は人生指南書ではありません。したがって、未来に対してこうすべきだなどという提言は全くされていません。ひたすら日本人社会を分析しているだけです。じゃあ、我々はどうしたらいいのか?これは難しい問題です。
確かに、日本人的社会では良い点もたくさんあるのです。人間平等主義は「出来ない」者でも受け入れられ、そういう人たちに絶えざる努力を促します。また、生まれながらの資格に左右されないので、身分や階級の違いがほとんどないわけです。しかし、その一方徹底的な序列により、若い能力の芽を摘んでしまうようなことが往々にしてあり、それが努力より発想が重要な分野において大きく立ち後れる原因にもなっています。
まずはこの日本的な序列(上下関係)と能力主義をどのように折り合いをつけていくのか、これが取りあえずの日本人の課題なのかもしれません。
パウル・ヒンデミット著/佐藤浩訳/音楽の友社
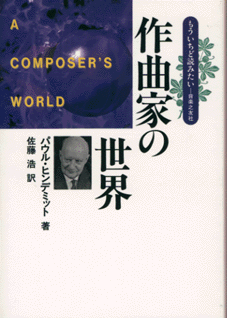 ご存知、今世紀の作曲家ヒンデミットによるこの著作は、作曲という行為が関わる全工程に対してヒンデミット自身の考え方を述べたものです。どちらかというと、学術書ではなくて音楽愛好家に向けた内容ですが、話題はいろいろな方面にわたるため、この本を読む人たちにもそれ相応の文化的知識を要求します。ヒンデミット自身、理論家でもあり教育家でもあり、その多方面にわたる知識には脱帽というしかありません。ですから、大作曲家が素人に対して作曲とはこんなもんだよ、というのを伝えている本だと思って読んだら、かなりしんどい思いをして読まなければいけないでしょう。むしろ、ヒンデミットは音楽という題材を使いながら、社会や哲学のようなジャンルさえ視野に入れているように思えます。
ご存知、今世紀の作曲家ヒンデミットによるこの著作は、作曲という行為が関わる全工程に対してヒンデミット自身の考え方を述べたものです。どちらかというと、学術書ではなくて音楽愛好家に向けた内容ですが、話題はいろいろな方面にわたるため、この本を読む人たちにもそれ相応の文化的知識を要求します。ヒンデミット自身、理論家でもあり教育家でもあり、その多方面にわたる知識には脱帽というしかありません。ですから、大作曲家が素人に対して作曲とはこんなもんだよ、というのを伝えている本だと思って読んだら、かなりしんどい思いをして読まなければいけないでしょう。むしろ、ヒンデミットは音楽という題材を使いながら、社会や哲学のようなジャンルさえ視野に入れているように思えます。
そのような内容のヘビーさの他に、もう一つこの本が面白いのは、ヒンデミットが気に入らないと思っていることに対しては相当に辛辣な表現で書かれているということです。もちろん、すでに作曲家として十分なステータスを得たうえで、晩年に書かれた本ですから、これはもう誰も怖くない境地に達していたことは想像に難くありません。だからこそ、ヒンデミットが音楽に対して、作曲に対してどのような考えを持っていたか、率直なことが伝わる、生の作曲家の声が伝わる非常に興味深い本になっているのです。
とはいえ、正直なことを言えば、私自身この本の内容に100%共感するものではありません。音楽家を巡る社会的環境や、演奏家との人間関係など、実際的な面に関する記述ではかなり面白く読めるのですが、作曲家の想像の源とか、作曲家の使命みたいなもの、あるいは音楽は何を目指すものなのか、といった哲学的な考察の部分では、私の思いと相当隔たりがあります。
しかし、一般的なクラシックファンならヒンデミットのような考え方には共感する人も多いでしょう。つまり、私から見ればあまりにもドイツ的で、いわば崇高な物に対するあくなき希求に貫かれているのです。もちろん、ヒンデミットの知性からすれば、作曲に神懸り的な霊感などを認めたりしていませんし、権威主義的に過去の大作曲家を必要以上に持ち上げたりしていません。しかし、音楽に対して「道徳的、倫理的」という表現で相対し、また過度な美しさ、甘美さに陥ることを厳しく警告するなど、音楽の享楽的性格だけが前面に出ることに厳しく警告しています。そして、チャイコフスキーやドヴォルザークを、その理由で批判さえしています。
一歩下がってフフンといっているような諧謔的傾向を持ったフランス音楽が好きな私としては、こういった内容では、やはりフフンなどと思ってしまいます。ヒンデミットにとっては、多分同時代に生きたプーランクなど、批判の対象でしかなかったことでしょう。逆にフランス人もこういったヒンデミットの態度にはどこか鼻で笑ってしまうような態度を取っていたかもしれません。
もちろんどちらの態度がよいか、という問題ではなく、それぞれが考える享楽的なものの意味とか知性への対し方の違いが出ているだけと取るべきでしょう。
さて、それはさておいても、この本は面白いことが結構書いてあります。
上のようなことを言うと、ヒンデミットがかなり現代音楽に近い創作家だったように感じる人もいると思いますが、むしろヒンデミットは和声や旋律の力を信じ、それでいてあくまでそれらは技術的な問題と割り切って創作家の大きな目標とは切り離して考えようとしています。したがって、作曲技法そのものが作曲行為のモチベーションとつながっている現代音楽については、相当な批判を展開しています。ことに12音音楽に対する批判は、私にとっても我が意を得たり、といった感じでした。後半では、こういった現代音楽の潮流がまるで教祖をおがむ新興宗教の様相を呈しているとも言っています(もちろん、教祖様はシェーンベルグでしょう)。特に演奏家と作曲家が分業した結果、このような音楽が多くの人を惑わしていることを嘆き、作曲家自身が演奏できる音楽家であるべきと説いています(ヒンデミットは若い頃有能な演奏家でもあった)。
また、現代における必要以上の指揮者賛美についてもかなり辛辣な表現で書かれています。つまり、今の民主的な世の中で独裁者はゆるされず、指揮者とは聴衆が高いお金を払って自分自身の独裁的傾向を投影し満足するためにある存在なのだ、とのこと。クラシック音楽にありがちな指揮者礼賛、そして意味のない言葉が並べられたその音楽への賛辞に対して、なんとなくいやーな感じを持っている私にとって、ちょっぴり小気味良く感じたところでもありました。
また全体にわたって、合唱、特に小人数のアンサンブルに対して非常に好意的です。人の声が、すべての音楽の元であり、その音楽を極めることがアンサンブルの中にあるのなら、音楽の理想の形態は声楽アンサンブルということになるでしょう。そして、作曲家も社会的な成功が十分に得られないうちは、素人向けのアンサンブル音楽をもっと書くべきだ、と諭しています。それこそが、今の商業主義に毒された音楽業界を健全にする方法だと言うのです。これはヒンデミットが精一杯考えた現実との折り合いの方法なのでしょう。
ところで、この本は1952年に書かれています。ほぼ50年前ですが、意外と現代の音楽の様相を見比べてもその内容が古めかしい感じがしなかったのは、やはりヒンデミットの眼が鋭い部分をついているからでしょうか。そのヒンデミットが、今の状況を見たらもちろんもっと哀しんでいるには違いないのですが、意外と現在あるさまざまな潮流を冷静に判断した上で、クラシックの枠をさえ飛び越して新しい音楽を目指すのかもしれません。
佐藤雅彦 竹中平蔵著/日本経済新聞社
 最初にこの本を手にしたときのイメージは、経済素人である佐藤氏が専門家に経済の基本的な知識などを対談型で教えてもらう、という感じでした。佐藤雅彦というとやっぱり「だんご三兄弟」ですから、何となくですけど本当に経済の入門書ってふうな気がしていたのです。私は工学部出身だし、今まで経済に興味があったわけではないのですが、やっぱり世の中を知るには経済学の知識も必要だよな、なんて漠然と思っていたわけで、ちょうどこの本を見たときに「これならいけるかも」なんて気持ちでつい買ってしまったのです。
最初にこの本を手にしたときのイメージは、経済素人である佐藤氏が専門家に経済の基本的な知識などを対談型で教えてもらう、という感じでした。佐藤雅彦というとやっぱり「だんご三兄弟」ですから、何となくですけど本当に経済の入門書ってふうな気がしていたのです。私は工学部出身だし、今まで経済に興味があったわけではないのですが、やっぱり世の中を知るには経済学の知識も必要だよな、なんて漠然と思っていたわけで、ちょうどこの本を見たときに「これならいけるかも」なんて気持ちでつい買ってしまったのです。
しかし、当然というべきか、自分が当初思っていた感じとは随分違う感触の本でした。
確かに経済のいろんな言葉についての説明とか、そういう部分はあるのですが、そもそも私にはそれ以前に経済について知らなきゃいけないことが多すぎて、結局理屈としての経済学を知るという意味ではちょっとこの本の方向性は違います。
この本について簡単に言ってしまえば、クリエーターである佐藤氏と経済学者である竹中氏が時事ネタを元に経済学的に語り合う、といった感じの本なのです。もちろん、経済学の具体的な内容については佐藤氏が竹中氏に質問して、それに答えるという形なのですが、それにしても教えてもらうにしては佐藤氏は物分りが良すぎるのですね。
一般には佐藤氏は「だんご三兄弟」のイメージが強いわけですが、40歳まで電通の社員、そして今ではCM制作などを手がけるクリエータで、だからこそ世の中のいろいろな動きについても詳しいし、妙に物知りなわけです。この本の面白さは、経済を知る、ということより経済をネタに二人が理想の社会とはどんなものであるか、それを経済学的に考えてみましょう、といったところにあるのかもしれません。
とはいえ、まずは経済の初歩的な命題である「お金」「株」「税金」の話からこの本は始まります。
株に関しては興味深い話があったので、ちょっと紹介しますが(わかる人にはそんなの当たり前だろ、と言われそうだけど)、この株式会社という制度は1600年に設立された東インド会社から始まっていると言います。なぜ、そんな形を始めたかと言うと、当時インドに行って香辛料などいろいろなものを仕入れに行くのは大変な危険が伴い、また莫大な初期費用が必要でした。もちろん、それによる利益も大きいものだったのですが、まずは事を始めるのに資金が要ります。そこで、株式を買ってもらいその費用を得て、その事業で儲けたお金を出資者が出した金額に応じてシェアするのです。
当時は、一回の航海につき一度きり出資してもらい、その利益を分け合ったらそこで解散という非常に原始的な仕組みであったのですが、その事業を永続的に行おうとすると、出資したお金を返してほしい、とかいうことが起きるわけで、そのためにいくら出資したかという証文そのものが売買されるようになっていきます。つまりこれが株式市場なわけです。
しかし、そう考えてみると株の基本的なメリットというのは、売却益によるものではなくて、利益の配当、ということになります。一般的に株をやっているというと配当で儲けたってことはあまり聞かないのですが、そちらのほうが株で儲ける本質だったわけです。
特に日本においては、この株の配当というのがほとんど行われていない(というか不当に安い値段)のが実情らしいのです。日本企業はお互いの株を会社同士で持ち合うようなことが一般的で、一般株主への配当が不当に扱われてきました。その結果、普通なら配当に回すお金を会社の設備投資に回すようなことをして日本企業は発展してきたのです。
このあたり、企業に対する感覚が欧米と日本ではかなり違います。
欧米においては、株主が会社のオーナーであり、その意向が経営に大きく影響しますが、ご存知のとおり日本の株主総会では満足な議論などされておらず、実質日本においては会社はその経営者と従業員のもの、という感覚がものすごく強いのです。よく「ウチの会社は...」なんて言いますが、本来会社の所有者は株主なわけで、そこに現実と建前の大きなギャップが存在しています。
以上のように、この経済を論ずる中で、日本の経済政策のあり方、様々な慣習にまで問題点を浮き彫りにし、そして批判するような部分が随分あります。確かにこの本を読んでいるといかに日本の経済政策が迷走しているか、納得させられます。それは中盤において、アメリカの経済、アジアの経済、ユーロの話などの中でさかんに出てくるのです。
最後のほうでは、経済学の新しい流れや将来の展望について語られます。
経済学はお金の流れを徹底的に即物的に扱うことで発展してきました。経済学的に言えば、人間というのは単なる「労働力」に過ぎないし、その消費行動は常に自分の欲望と経済力を天秤で計っている欲望の固まりのような存在を前提としているのです。ところが、人間には道徳的、倫理的な価値基準もあるし、生きがいとか自己実現の場としての労働という側面もあるわけで、本当の経済活動の予測にはそういったあいまいなパラメータを論じていく必要があります。そして、そのような時代の流れからいくつかの新しい経済理論も誕生しているそうです。
佐藤氏の言葉で印象的なのは「今の世の中はブレーキのないジェットコースターのようなもの」というところです。社会主義国の崩壊から民主化を経て、市場経済のマーケットはここ10年で2倍になったといいます。つまり、これによりさらなる競争の激化が起こっているのです。この未曾有の経済競争時代が果たして、人間にとって幸福なのか?そういった点について佐藤氏は尋ねるわけです。歌い手や作家のスター性だけでどんどん消費されていく流行歌、本質とは違う余計なものをつけて差別化を図るメーカーなどなど、競争激化からはおかしなことも生まれてしまいます。もちろん竹中氏はそれに対して明確な答えを持っているわけではないですが、社会全体がより良くなるような経済理論のいくつかを紹介しています。
経済学の本質とはよりよい共同体をいかに作るか、と本書では述べています。社会的幸福感が経済と無関係ではない以上、我々がいかに生きていくか、に対する経済学的な回答はより重要になってくるのかもしれない、とこの本を読んで感じました。
「最近話題のビョークというミュージシャンが主演、及び音楽を手がけているミュージカル映画」と、これだけの予備知識で見に行ったのですが、正直言ってあまりに最初の印象と違う、凄まじく強烈な映画でした。
この映画を見終わった時点で感じた印象は一言で言えば「救いようがない」ということに尽きます。映画を見終わって観客が思わず流す涙も、感動したという感じとはちょっと違って、この救いようのなさに打ちひしがれるから、ではないでしょうか。しかし、後から後からこの映画を反芻すると、その背後に潜む様々な哲学的意図を感じますし、緻密に計算された構成にも驚かされるのです。
それにしても、正義感に溢れ、安易なヒューマニズムに毒されたアメリカ映画を普段楽しんでいる我々には、この映画の衝撃度は耐えられないものではないでしょうか。子供でもわかるような勧善懲悪、その予定調和の世界に、人々は安心を求めます。しかし、現実は違うのです。世界に生きている誰もが自分を正しいと思い、逆に誰もが少なからず悪い心を持っている。そんな細やかな心の動きにすれ違いが起きて、それが増幅されてしまったときに悲劇が起きます。そんな、日常に潜む悲劇をこの映画は鋭く抉り取り、見る者の前に突き付けてきます。一見、淡々と進行する物語には起伏がないように見えて、登場人物のたわいない一挙一動が人の心の最も深いところにグサグサと突き刺さってくるのです。
そんな雰囲気がアメリカ映画とはあまりに違っていて、ヨーロッパ的なものを感じさせます。
それにしても最初の40分間はあまりに変化がなく、いったいどうしたことかと思いましたが、最初のミュージカルの曲が現れたところでその疑念はいっぺんに吹き飛びました。このミュージカル部分を際立たせるために、ここまであえて引っ張ったのでしょう。このような暗い内容のストーリーの中で、ミュージカル部分だけは全く異様に輝いています。
また、全てのミュージカル部分は主人公セルマの白昼夢という設定になっており、「夢の中だけでは恐ろしいことは何も起こらないの」という彼女の言葉があまりに痛切に響きます。まさに、目が見えなくなっていく彼女にとって、夢の中だけが現実だったのかもしれません。
ミュージカルシーンでは、それまでのドキュメンタリータッチのカメラワークが、急に人工的でエンターテインメント性の高いカメラワークに変わります。些細な騒音がリズムに変わり、白昼夢に誘われる段階で、音楽に変わっていくのもなかなか面白い。彼女の全ての敵は、音楽の中で味方に変わり、主人公と一緒に踊り、歌います。子供が心に描くような自分にとって都合のよい空想...だからこそ、よけい現実の悲しさが心に暗くのしかかります。
それにしてもこの映画は深い。この映画のことを考えると、あまりにいろいろな思いが交錯し、一つにまとまりません。今、こうして書いていてもこの映画を理解するためのいくつものアプローチが思い付きます。でも、いざ言葉にしようとすると陳腐な表現ばかりで、どうしても言葉で語ることが出来ない自分を感じます。それほどまでに、この映画には多義的な解釈や、深層心理に訴える何かがあるのでしょう。
ただ一つだけ、私が思いついた面白い解釈があります。
それは、この映画とキリストの受難とのアナロジーです。あるいは、この映画全体がバッハの「マタイ受難曲」のような構造を持っているとも考えられます。(以降は映画を見ようと思っている方は読まないほうがいいかもしれません)
例えば、映画冒頭で全く暗闇のままでこの曲のテーマが演奏されますが、これは受難曲の冒頭の序曲に相当します。逮捕、裁判から処刑にいたる過程など、まったくイエスの受難そのものではないでしょうか。
イエスは十字架にかけられ、一瞬弱気になり「神様、なぜ私をお見捨てになるのですか」と言います。セルマも同じように、弱気になりますが、歌を歌うことで自分を取り戻します。
そう考えると、この最後の結末は全く自明なものだったとも思われるのです。逆に全ての物語がこの一瞬のために逆算して作られたような、そんな気がします。
つまり、セルマ=イエス・キリスト。過酷な運命に耐え、自分の意思を貫き通すその凄まじい生き方。彼女は、確かに一見おとなしそうだけど、自らの目的のためだけにそこまで強い人間になれる、ということが、宗教的な高みと並置させられているのです。そう考えると、受難曲というのも相当ショッキングな物語なのだな、とあらためて思いなおしてしまいます。
この映画、とても万人にお勧めするとは言い難いものがあります。嫌悪感を感じる人もいるかもしれません。しかし、何十年たっても、常に一定の人達を魅了しつづけるカルト的なヒットをするような気がします。
Mike Gancarz著 芳尾桂監訳/オーム社
 UNIXとは何かご存知でしょうか。
UNIXとは何かご存知でしょうか。
一言で言えばWindowsのようなOSの一つなのですが、一般のパソコンで使われるようなOSではなく、ワークステーションと呼ばれる技術者向けコンピュータで最も良く使われているOSなのです。
もちろん、私自身も業務上全く無縁ではなかったわけですが、正直なところなるべく避けて通ろうと思っていた^^;技術でもありました。というのは、実際に業務上でプログラム開発するときはほとんどパソコンの上で行っていて、ワークステーションはファイルサーバーとして利用していたのですが、自分自身が頻繁にこのサーバーを利用することが少なく、たまに使うたびにあまりに面倒なUNIXコマンドを調べながら使うのがすごくしんどかったからです。
ただでさえコマンドを憶えるのが苦手な私としては、山ほどのコマンドを頭に憶えこませ、単調なコマンドライン型のインタフェースを強要するUNIXマシンははっきり言って嫌なものでしかありませんでした。
早く世の中からUNIXなんて無くなればいいのに...とさえ、思っていたのですが、実際のところはどうだったのでしょう。確かにマイクロソフトは、この市場に目をつけ、Windows
NT, Windows2000とサーバー市場にも殴り込みをかけ、UNIX市場を脅かそうとしています。
しかし、そもそもインターネットの基本的な技術は全てこのUNIX上で出来たものであり、今では逆に多くの人がメールのSMPTE、POPとか、HTTP,
FTPなどのサービス、IPアドレスの仕組み、CGIやPerlなど、インターネットの知識として多少なりとも関わらざるを得なくなってしまっています。おかげで、UNIXはなくなるどころか、しつこいくらいにコンピュータ周辺技術にまとわりつき知らないうちにその勢力を増やしているのではとさえ感じます。
昨今はこのUNIXをパソコンに移植したLINUXと呼ばれるOSが登場し、オープンソースの考え方とあいまってさらなる広がりを見せています。
そんなおり、ソフトウェアのプロを自他ともに認める某友人の勧めで、この本を読みました。
この本には目新しいことが書いてあるわけではありません。それでも、私自身がこれまでUNIXに感じていた漠然とした敷居の高さというのがまさにUNIXの思想の根幹であったということに気付くことが出来、自分にとっても大変刺激に富んだ内容だと感じたのです。
最初の一言が衝撃的です。ちょっと長いですが抜き出します。
『UNIXの創造者たちは、ある極端なコンセプトから始めた。ユーザーは初めからコンピュータを使えるとみなしたのだ。UNIXは「ユーザーは、自分が何をしているかを分っている」との前提に立っている。他のオペレーティングシステムの設計者が、初心者から専門家まで幅広いユーザーを受け入れようとして苦労しているとき、UNIXの設計者たちは「何をしているのか分からないのなら、ここにいるべきでない」という不親切きわまりないアプローチを選んだ。』
そ、そうだったのか!それで全て納得がいく、と私は思ったのです。
私がこれまでUNIXを受け入れられなかったのは、最初のコンピュータ体験がマッキントッシュであったというのも大きく影響しています。むしろマック信者であった私は、ある意味このUNIX哲学と正反対の立場でコンピュータを評価していたわけです。
これまで、職場でも異常にテキストファイルで格納することにこだわる人たちがいました。これもUNIX教の考えなのでした。究極のファイル形式とはUNIX教の人たちにとってテキストファイルなのです。
そして、WYSIWYG(だっけ、要するに「見たままのものが得られる」というマック教の考え)を否定し、例えばインターネットの標準形式であるHTMLのような形式を良しとするのもUNIX的な発想です。しかし、だからこそ、HTMLはこれだけ広く世の中で使われることになったとも言えるのです。
それでは、ここに書いてある内容がことごとく自分の考えに反しているのか、というとそうではないのです。
ソフト開発をする者にとって、有用な教えが実はこの中にたくさん詰まっています。そして読む度に、「ああ、この部分をあの人にも、あの人にも読ませたい!(あの人には特定の上司の名が入る^^;)」とついつい思ってしまうのです。
特に印象的なのは「効率より移植性を選べ」という点。
簡単に言ってしまえば、「スピードが遅くなっても将来使いまわしの出来るプログラムを書け」ということ。
これの悪例として、ATARIという昔のゲーム専用コンピュータの話が出ています。ATARIは当時、大変爆発的なヒットをしたコンピュータでしたが、安いハードで最高の性能を出すために、ハード依存のぎちぎちのチューニングを施したコードが書かれていました。確かに非常に安価でテキパキと動くATARIは登場当時大変売れたわけですが、その後ハードが新しくなるたびにソフトを書き直さなければいけなくなり、そのためのコストも時間も馬鹿にならなくなりました。それは結局コンテンツが揃う時期が遅れることになり、時代の流れについていけなくなってしまったのです。
これを聞いて、うなづくエンジニアは多いはずです。同じようなコードを何度となく書いてきたことか。一度書いたものがずっと使い続けられたなら、というのはプログラマの切実な願いです。そして、それを可能にするためには、私たちの努力だけでなく、マネージ側の理解が欠かせないのですよ、ホントに。
◇戻る◇

 談話などで日本人について論ずることが良くあります。多分、私の中でかなり興味あることなのでしょう。それで本屋に行っても、ついついその手の本を手にとってしまうのです。たいていは人生指南書的なものがほとんどで、内容的にはたいしたものがないのが常です。そうした本を見るにつけ、もっと学術的に日本社会を論じたものはないのか、という気持ちが私の中で感じていたところでした。
談話などで日本人について論ずることが良くあります。多分、私の中でかなり興味あることなのでしょう。それで本屋に行っても、ついついその手の本を手にとってしまうのです。たいていは人生指南書的なものがほとんどで、内容的にはたいしたものがないのが常です。そうした本を見るにつけ、もっと学術的に日本社会を論じたものはないのか、という気持ちが私の中で感じていたところでした。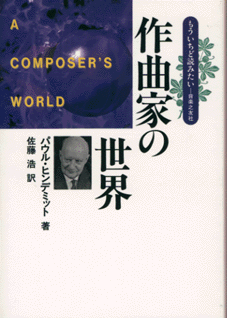 ご存知、今世紀の作曲家ヒンデミットによるこの著作は、作曲という行為が関わる全工程に対してヒンデミット自身の考え方を述べたものです。どちらかというと、学術書ではなくて音楽愛好家に向けた内容ですが、話題はいろいろな方面にわたるため、この本を読む人たちにもそれ相応の文化的知識を要求します。ヒンデミット自身、理論家でもあり教育家でもあり、その多方面にわたる知識には脱帽というしかありません。ですから、大作曲家が素人に対して作曲とはこんなもんだよ、というのを伝えている本だと思って読んだら、かなりしんどい思いをして読まなければいけないでしょう。むしろ、ヒンデミットは音楽という題材を使いながら、社会や哲学のようなジャンルさえ視野に入れているように思えます。
ご存知、今世紀の作曲家ヒンデミットによるこの著作は、作曲という行為が関わる全工程に対してヒンデミット自身の考え方を述べたものです。どちらかというと、学術書ではなくて音楽愛好家に向けた内容ですが、話題はいろいろな方面にわたるため、この本を読む人たちにもそれ相応の文化的知識を要求します。ヒンデミット自身、理論家でもあり教育家でもあり、その多方面にわたる知識には脱帽というしかありません。ですから、大作曲家が素人に対して作曲とはこんなもんだよ、というのを伝えている本だと思って読んだら、かなりしんどい思いをして読まなければいけないでしょう。むしろ、ヒンデミットは音楽という題材を使いながら、社会や哲学のようなジャンルさえ視野に入れているように思えます。 最初にこの本を手にしたときのイメージは、経済素人である佐藤氏が専門家に経済の基本的な知識などを対談型で教えてもらう、という感じでした。佐藤雅彦というとやっぱり「だんご三兄弟」ですから、何となくですけど本当に経済の入門書ってふうな気がしていたのです。私は工学部出身だし、今まで経済に興味があったわけではないのですが、やっぱり世の中を知るには経済学の知識も必要だよな、なんて漠然と思っていたわけで、ちょうどこの本を見たときに「これならいけるかも」なんて気持ちでつい買ってしまったのです。
最初にこの本を手にしたときのイメージは、経済素人である佐藤氏が専門家に経済の基本的な知識などを対談型で教えてもらう、という感じでした。佐藤雅彦というとやっぱり「だんご三兄弟」ですから、何となくですけど本当に経済の入門書ってふうな気がしていたのです。私は工学部出身だし、今まで経済に興味があったわけではないのですが、やっぱり世の中を知るには経済学の知識も必要だよな、なんて漠然と思っていたわけで、ちょうどこの本を見たときに「これならいけるかも」なんて気持ちでつい買ってしまったのです。 UNIXとは何かご存知でしょうか。
UNIXとは何かご存知でしょうか。