ウォルター・ワンゲリン著/仲村明子訳/徳間書店
 キリスト教徒でない人でも、聖書という書物が世界中で読まれ、また多くの芸術、文化の源になっていることは誰でも知っていることでしょう。ところが一度その中をひも解いてみようとすると、なんとも読みにくい断片的な言葉の切れ切れが書いてあるだけで、背景がわからないと言葉の意味も全く分からないものです。
キリスト教徒でない人でも、聖書という書物が世界中で読まれ、また多くの芸術、文化の源になっていることは誰でも知っていることでしょう。ところが一度その中をひも解いてみようとすると、なんとも読みにくい断片的な言葉の切れ切れが書いてあるだけで、背景がわからないと言葉の意味も全く分からないものです。
最近は結婚式のときだけ、にわかクリスチャンになる人も多く、その際に牧師さんが聖書から何やら引用してくるわけですが、面と向かってちゃんと説明してもらうと、状況が状況だけに妙に感慨深く心に染みてきたりするものです。
この本は、私のようにクリスチャンではないけど、おおざっぱに聖書の内容を把握したいという人にはうってつけです。特に、合唱をやっていると当然ながら宗教音楽に触れることもあるわけですが、モテットと呼ばれる合唱曲の歌詞が聖書から選ばれることも良くあるのです。ただ、その詩は非常に短いものだから、その前後の背景がやはりよくわからない。そもそも、それらの曲は、すでにその言葉の背景を知っているキリスト教徒のために作られたからなのでしょう。そういった意味でも、この本はためになると思いました。
小説「聖書」は旧約篇と新約篇の両方が出ています。私は両方買って、2ヶ月ほどかかってようやく読破したところです。
旧約篇では、だれしもアダムとイヴ、カインとアベル、ノアの方舟、バベルの塔などの話は知っていると思いますが、これらの話は最後にちょこっとでるだけで、この本の構成はアブラハムからはじまるイスラエルの民と国の形成の歴史が中心となっています。実際ほとんど神話みたいなものだと思っていたんですが、アブラハムのあたりはあやしいとしてもモーセなどは歴史でも習ったので、それ以降はほとんど事実に即しているわけです。つまり、旧約聖書とはユダヤ民族の歴史書と言えることがようやく実感としてつかめたわけです。
しかし、そう考えると一民族の歴史書がこれだけ世界中でスタンダードになること事態が不思議なことです。現に、ユダヤ民族を嫌う人もたくさんいるわけですし(無論、スタンダードになったからとも言えますが)。また、ユダヤの神というのは、人に対して全く容赦がなく優しい存在ではないのです。ユダヤ民族だけにしか幸福をもたらさない非常に排他的な神でもあり、その中に民族の選民思想があるのは疑いのないものでしょう。戦争や諍いがあっても、神の力で敵方に大きな被害を与えるし、また自民族であってもユダヤの神を信じないものには激烈な懲罰が与えられるのです。
これは、私の宗教感とは大きく隔たっているのですが、逆にそれだけ神の仕業が過激であるほど、その信仰も過激であるのでしょう。でなければ、2000年の時を超えても、イスラエル国家を建設しようとするユダヤ人の気持ちを理解することはできないのではないでしょうか。
実際、中東の一民族に過ぎなかったユダヤ人は、この聖書という書物の存在のためにここまで注目を浴びているのかもしれません。これだけ昔に長大な歴史と激烈な思想を持った書物はなかったでありましょうから。日本の古事記や日本書紀でさえ、さらに1000年以上あとのことですし。
さて、新約篇ですが、こちらはご存知のとおり、キリスト教の聖典そのものです。キリスト生誕から布教、受難、復活までの出来事が書かれています。キリストもユダヤ人であったのですが、彼はモーセから綿々と続くユダヤの律法を犯すような行動から同じくユダヤの民から激しく非難を受け、最終的には十字架にかけられます。しかし、キリストはユダヤ教を否定したわけではない。なぜなら彼の説教には旧約聖書の様々な内容がベースになっているからです。そして、キリストは民衆に向かって「新しい契約が始まった」と言うのです。
キリスト教がこのように世界宗教に発展したのは、ユダヤ教の持つ排他性を廃したことが大きいと思います。つまり神を信じるものなら民族は関係ないということです。実際、ユダヤ人以外に弟子が布教を始めたのはキリストの死以降なのですが、それが許されるベースの思想がキリスト教にはあったのでしょう。
実際の話、キリストも随分過激な人間なのです。また、人間として言うならある種傲慢で、妥協ということを全くしないわけです。神の子が妥協してしまったら元も子もないですが、当時のユダヤ教を仕切っていた人からみれば全く鼻持ちならない、災いをもたらす者としか思えなかったことでしょう。しかし、その傲慢さはそのままキリストのカリスマ性となり、あまりに激烈に生き、あっという間に処刑されてしまったので、逆に弟子にとってのキリストの記憶は、拭い切れないほどの鮮烈なものとなったに違いありません。実際、キリストの処刑のとき弟子は誰一人同様な罪を問われなかったにも関わらず(ペトロのようにキリストを否認までするのに)、その後ほとんどの弟子が布教と厳しい殉教の最期を遂げるのです。
この2冊、いくら読みやすく小説の形になっているとはいえ、おびただしい人物の名前、出来事が錯綜し出してくると、意識が朦朧としてくるので、睡眠剤としての効果もありです。そのまま夢の続きで、聖書と戯れるというのもまた一興かと思いますが、いかがでしょう。
J-POP進化論【BOOK】
佐藤良明著/平凡社新書
 この本の題名だけ聞いて、どのような内容の本を想像するでしょうか?
この本の題名だけ聞いて、どのような内容の本を想像するでしょうか?
J-POPとあるので、日本の歌謡曲やニューミュージックあるいはロックだということはわかるけど、それをどのように論じているのか、興味があってついつい買ってしまいました。
この本の大きな特徴は、音楽の叙情性とか、アレンジとか、歌い方とか、そういう音楽の表面的で曖昧なものを捉えているのではなく、はっきり言ってしまえば、音楽のとくに旋律の問題をあくまで学術的なアプローチで論じているということになるでしょう。
作曲という観点から学ぶ学問としては、対位法とか和声法とか管弦楽法とかいうのがメインだと思います。この本にあるような旋法についての学問は、むしろ民族音楽や古い教会音楽をやっている人に興味のある話題かも知れません。それらの理論を、J-POPに当てはめつつ、日本の流行歌の変遷、もっと言えば日本人の戦後における心の変化を論じているのがこの本の面白いところです。
さて、日本的な旋律といって思い浮かべるのは四七抜き(「よなぬき」と読む。ファとシを抜いた音階)旋法だと思います。四七抜きの旋律で挙げられているのはキャンディーズの「春一番」、美空ひばり「真赤な太陽」など。しかし、この四七抜きは決して日本古来のものではないというのが著者の意見です。そもそも、日本にはテトラコルド(4度の積み重ね)による民謡調が基本でした。これも、ドレミソラと構成音の上では四七抜きと同じなのだけど、終止音が違うのです。四七抜きは西洋音階を日本風に導入するための折衷案であり、最終的にはドの音で旋律は終わる。民謡調はレなどで終わるのです。
明治期に西洋音楽を導入した日本では、もとよりあった民謡調の心とうまく折り合うために四七抜きによる旋律をたくさん作りました。しかし、歌謡曲の近代化は、西洋への憧れからだんだん四七抜きを離れていきます。このあたりの曲を著者は日本人が背伸びをして無理矢理西洋風の曲を作っているが、日本的な部分から離れることができないムード歌謡の世界として捉えています。
このムード歌謡の旋律的な特徴は#やbが多い、ということです。とくに著者は「ソ#→ラ」の動きに注目し、この例にかなう曲をいくつか挙げています。しかし、この疑似西洋的な旋律はGSの時代になって「ソ→ラ」になっていきます。これは、ブラックの要素が日本に入ってきたためですが、結局のところ日本人が持つ四七抜きへの郷愁とあいまって、また四七抜き的な旋律が復権してくるわけです。
このあたりは、合唱でルネサンス音楽などを歌っている経験から、とても面白く感じたところでした。ルネサンス音楽は基本的に教会旋法を中心に旋律が作られています。ポリフォニー音楽の最盛期では、即興的に特定の音を半音変化させることがありました。ムジカフィクタといわれる音符の上の#やbのことです。この#やbのついた音は機能和声の世界の導音としての役割を果たすことになり、民謡調が機能和声へと進化する大きなきっかけとなりました。その後、西洋音楽は「ソ#→ラ」を美しく感じる機能和声の世界へと変っていきます。こう考えると機能和声的な変化音とは人工的なものであるような感じを受けますし、そのために民族が持つ純朴な叙情を失ってしまうこともあるのではないかと感じました。
後半では、特に最近のJ-POPで多い、しゃべり口調の歌について書いています。元祖とも言えるのがサザン。「勝手にシンドバッド」の歌詞情報の密度、巻き舌によるラ行、シンコペーションを多用したトリッキーな独特な歌い口が多くの日本人の心を捉えました。
そもそも日本人には一拍を四つに感じる力をもともと持っているそうで、七五調や五七調などもそれが基本となります。これと、近年の強いビートとラップ調の流行がうまく噛み合って、日本の歌の幅が広くなる可能性を持っている、と著者は言います。
歌は世につれ、といいますが、そのとおり歌はどんどん変っていきます。常にその時代の雰囲気を反映させながら。
そして、気にもとめずに作った旋律から、そのときの日本人の心が伝わってくるのは何とも面白いことです。
これから先、流行歌がどのように変っていくかは誰もわかりません。ただ、単なる西洋礼賛ではなく、また単なる民族的な音楽への回帰でなく、私たちの意識はもっともっと複雑な要素を持った音楽をこれからも作りつづけていくことでしょう。
オペラ「三郎信康」【CONCERT】
日時、場所: 8月29日(日)午後2時開演、アクトシティ浜松大ホールにて
 私の身の回りの人も数多く関わっていたこの創作オペラの演奏会に行ってまいりました。
私の身の回りの人も数多く関わっていたこの創作オペラの演奏会に行ってまいりました。
どうも地方の創作オペラというと村おこし的でいかにもといった題材で、はっきりいっていい印象を持っていません。そもそも、自分がそれほどオペラファンというわけでもないので、この浜松で行われた創作オペラに関しても、最初からいい印象を持っていなかったというのが正直な気持ちでした。
もちろん、このオペラも、浜松ゆかりの作曲家、声楽家、地元の合唱団が関わり、浜松市が強力にバックアップし、そして題材は浜松に関わりのある悲運の武将を描いている、という点において、これまで私が抱いていた「いかにも」を地でいっています。
それでも、その「いかにも」を超えようとして、関係者がこのオペラ制作に熱意を持って取り組んだことがひしひしと伝わるよい演奏会だった、と私は思いました。
三郎信康とは、徳川家康の息子で、武田氏と密通しているという疑いから織田信長の怒りをかい、若くして切腹せざるを得なかった悲劇の武将です。この切腹までのドラマをこのオペラでは扱っています。
まず、この手の創作オペラの場合内容がクサくなり易いものですが、オペラ企画の当初より、綿密な取材が行なわれ、ある種の信念を持って台本が作られたことにより、リアイティが増し、ストーリーそのものを十分楽しめました。オペラの肝を押さえたストーリー展開と、一つ一つの台詞の的確さがうまくバランスが取れていたように思います。台本の渡部さんは声楽家でありながら、劇作家としての才能も十分に持ちあわせている方だと感じました。
台本に対して、一つ難を感じたのは、第2幕の最初から信康の切腹にいたるまでの経緯が今一つ明確に感じられなかったことです。あとで台本を読むとわかるんですが、実際なかなか言葉が聞き取れずに、あれあれ切腹しちゃうの、ってかんじで、大事な場面だけに、もう少しわかりやすさが欲しかったです。
作曲のほうですが、これは実は関係者からいろいろ噂を聞いていまして、どうもこのオペラの上演に際して、作曲者の力は非常に弱かったらしいのです(あるいは積極的に関わる立場にいなかった)。パンフレットにも書いてありますが、最初に書いたスコアの8割程度は書き直した、と言っています。指揮者はこの手の創作オペラに造詣のある人ということで、作曲者の意志に関係なく、音楽はばしばしカットされたり、書き直しになったりしたらしい。うーむ、いまどきこういった作曲家と指揮者の関係も珍しいと思いながら、なかなか面白いエピソードだと思いました。
私も二橋さんというこの作曲家は知りませんでしたが、なかなか立派な経歴を持っています。また今回の音楽も総体的にツボをえたよいものだと思いました。全体的なイメージとしては、ほとんど前衛的な音はなく、後期ロマン派的な音楽構成を持ちながら、時々フランス近代を感じさせるフレーズが出たりする感じでした。「愛」のテーマの重ねあわせなどドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」を思わせます(私の予想するに、結構聞いたんじゃなかろうか?)。このような市民オペラに前衛音楽など全く必要ないと私は思いますから、下手に有名な作曲家に頼んでとんでもない曲を作られるよりはよい結果を得たんじゃないでしょうか。
ただ、音楽全般にメロディが乏しいとちょっと感じました。このへんが、若干現代的とも思いましたが、最後の最後に出てきたようなやや通俗的なメロディをもっと恐れずに使ったほうが、聴衆の反応は良かったと思います。特に、重要人物のアリアにはもっと耳に残るフレーズがあっても良かった。
もう一つ、日本語の処理が気になりました。日本語をしかもオペラという形式の中で音符を与える行為は、確かに難しいもので、私がわずかながら聞いた日本のオペラはそれぞれ全く独自なレシタティーボの様式を持っています。
その中でも、二橋氏はかなり鋭角的なフレーズで日本語を処理しており、声楽家の立場からすると、実に色気のないレシタティーボに感じたと思われます。ただこの方法は、日本語が非常に聞き取りやすい、という利点も感じ、そういった意味では必ずしも批判しきれない気持ちがあります。いずれにしろ、日本語によるレシタティーボは、日本語オペラの永遠のテーマなのかもしれません。
さて、今回のオペラは、アクトシティ浜松大ホールの四面舞台をフルにいかす、というのが隠れたテーマとなっています。
台本作者も相当それを意識しているし、演出家はもちろんでしょう。
私は3階席でしたが、いやはや、なんともダイナミックでしたよ。あれはどう考えても観客に舞台の動きを見せたいという制作側の気持ちがみえみえですね。祭りのシーンで、舞台が回っているところなど、映画でカメラアングルが段々変っていく様子を思わせました。冒頭でも亡霊役が宙吊になって歌いました(もっと動かすと面白いけど、まあ無理でしょうか)。最後の最後、美しい梅の花のセットで誰もいなくなって合唱の声だけが聞こえる、というシーン。このまま舞台に誰も現れず静かに終わるんだなあ、なかなか渋いねー、と思っていたら、なんとセットがまるごと下に沈み始め、その後ろから山台に載った合唱団員が山台ごと前に移動してくるというとんでもない仕掛けでラストを飾りました。さすがにこの演出は、ちょっと...とは思いましたが、まあ市民参加のオペラということで大目に見ましょう。
ソリストは浜松ゆかりの、あるいは在住の声楽家ということで、もちろん超一流のオペラ歌手ではないわけですから、それほどシビアなことをいうつもりはありません。ただ、主役級である徳姫は、声にくせがあり、言葉が聴きとりにくく、あんまり印象は良くなかったです。台詞も多かったので、言葉が分からずストーリーが分かりにくくなったのは多少いらだちました。それに比べると、信康役の黒田晋也さんは良く通る声と、聞き取りやすい言葉でオペラを盛り上げていました。演技もうまかったですね。
長々と書きましたが、全体的には非常に良い印象を持っています。
このオペラが今後再演されるかどうかは、このオペラの面白さとは関係ない、むしろ日本の音楽界の持つ問題に踏み込むことになってしまうので、ここで述べるのはやめておきましょう。
でも、あれだけお金をかけて立派なセットを作ったんだから、せめてもう一個所くらいでやらしてあげたいと思うのが、人情というものです。そういう機会があればよいですね。
関係された皆様、ご苦労様でした。
黒い家【BOOK】
貴志祐介著/角川ホラー文庫
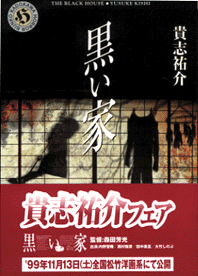 今、ちょうど映画でやっているんですね、この小説。
今、ちょうど映画でやっているんですね、この小説。
多分、それを新聞で見て頭のどこかにあったのでしょう。ついつい、本屋に行ったとき買ってしまいました。
最近は、ホラー小説大賞とかいう文芸賞があって、この小説はその受賞作なんですが、最近この手のエンターテインメント系で世に出てくる新しい作品の質には驚かされるものがあります。これでは、今まで作家と呼ばれていた人たちも、非常に焦って当然でしょう。
少し前に話題になった「パラサイトイヴ」の瀬名氏は、私と同じ大学の薬学部にいたそうで、確かに薬学、医学の知識を駆使し、また自分が生活している現場に近い場所に事件を設定することによって非常にリアリティのある内容が綴られています。もちろん、この手が今後何度も通用するとは思えませんが、それでも自分の得意分野+ストーリーテラーのうまさで、世に出てくるというのはこのジャンルの常套手段かもしれません。
この小説もまさにそういったパターンと言えます。著者、貴志氏は京大出身で、生命保険会社に勤めていた、と書かれてあります。この小説の舞台も京都、そして内容は保険金目当ての殺人事件を軸に書かれているわけです。(ちなみに「パラサイトイヴ」の舞台は明らかに東北大学)
それにしても、前半での生命保険会社の業務の内幕は、リアリティを超えて、驚愕ものです。多分、実際の保険会社ではそれほど派手にいろいろなことが起きるわけではないにしても、多かれ少なかれ実際にあることなのでしょう。
日本の場合、保険の勧誘員が何度も何度も訪ねてきて、そのしつこさでつい入ってしまうとか、親類がその仕事をやっていると入ってあげたりとか、自分ではつきまとわれてなんだか面倒な人たちだなあ、なんて思いつつもその商魂たくましさに落とされてしまう人も多いことでしょう。それで、実際契約してしまうと、毎月こんなに払っているけど、ほんとに自分のためになるのかなあなんて疑問に思うこともしばしばです。
しかしこの小説では、私たちが普段あまりお世話にならないであろう、保険の査定の職場を中心に話が進められます。これは、実際に保険を支払うための窓口と事務を行う職場なのですが、保険金目当ての偽装事故や、偽装入院(病院さえその肩を持つ「モラルリスク」病院というのがあるらしい)に対して調査などをしなければいけません。もちろん、そのようなことをする人たちですから、堅気ではないかなりヤバイ人間もいたりして、かなり危険な目に合うこともあるらしいのです。
そして、この小説はまさに、保険金目当てに周りの人間を殺していく、いわば殺人鬼のような人間と主人公の息をもつかぬ戦いが書かれているのです。
前述した、「パラサイトイヴ」あるいは「リング」「らせん」などのホラー小説は、基本的にはSF的な要素があり、現実の現象を超えてしまっている部分に恐怖を感じさせるわけですが、この本はあくまで実際に起こりうる事件であり、きわめて現実的な内容でもあります。ホラーであってもファンタジーとは決して言えない。サイコミステリーとでも言うのが一番合っているでしょうか。
だからこそ、社会の暗部に渡って隅々と描写していくこの小説の中身は、場合によっては直視できない内容であったり、生理的な悪寒を感じる部分もあるのは確かです。正直言って、ここで現れる殺人鬼の人間性自体が信じられないし、信じたくもないのです。そういえば、去年の和歌山毒入りカレー事件の某容疑者を思わせるような部分が多々あるのは感じました。それも広い意味での著者の人間観察力の鋭さから来ているものでしょう。
しかし、これだけのリアリティを持ったサイコ物のホラーは日本にはこれまであまりなかったんじゃないでしょうか。
それに何しろ、ストーリーの作りが上手いですね。余計な事実を大量に読者に与えず、主人公と同じレベルで読者も考え、推理し、そして判断させようとします。常に、物語の場の中に読者が放り込まれているように仕向けられているのです。後半は本当に手に汗握る、といった感じで、もう一気に読まずにはいられない状態になっていました。
映画の方は見に行かないと思いますが(多分)、氏の他の作品は読んでみようかな。
無罪モラトリアム【CD】
椎名林檎
TOCT-24065
 おっと、意外なものが、と思われた人も多いと思います。しかし、これは私にとって近年まれに見るヒットです。昔私がよく聴いていた筋肉少女帯とか戸川純とかと同じ系譜の、J-POP界の異端児とも言えるアーティストの登場なのです。
おっと、意外なものが、と思われた人も多いと思います。しかし、これは私にとって近年まれに見るヒットです。昔私がよく聴いていた筋肉少女帯とか戸川純とかと同じ系譜の、J-POP界の異端児とも言えるアーティストの登場なのです。
といっても、最近結構売れているみたいで、ここのところJ-POPに疎い私もようやくこのアーティストを知ることになったという次第。
椎名林檎というと、テレビで良く見る看護婦の姿とかちょっとセクシーな姿態とか、何やら怪しげな印象があったのですが、曲のタイトルとかも普通と変っていて、単に受け狙いだけでやっているとは思えないものを感じたのです。
実際、CDを買ってその詩を読んでみると、私の感じたとおり、一筋縄ではいかない尖がりまくった魂の叫びみたいのが響いています。ただ、その詩は場合によってはほとんど意味不明。かなりシュールな線を狙っている。そしてそのシュールさは、例えば中期井上陽水のような捉えどころのない浮遊感とは違う、もっとせっぱ詰まった軋む寸前の心の闇を描いています。その若さゆえの危なっかしさがもちろん大きな魅力なのでしょう。シュールといえば、シュールレアリズムの運動の中で自動記述法とかいう詩の作り方がありますが、まさにそんな感じの詩が目白押しなのです。
例えば、こんな詩
「飛交う人々の批評に自己実現を図り戸惑うこれの根源に尋ねる行為を忘れ...」
「朝の訪れを微塵も感じさせない夜 闇がこの先の日本を考えるのか...」
ほとんど何を言いたいかわかんない。それに単語の羅列でなくて、なんだかやたら長い文章っぽくて、これまでのシュールの系統と何か違う。また戸川純などと同じく、アブノーマルなセクシャリズムを感じさせる部分もあり、デカダンの匂いがプンプンしています。このあたり、もしかしたら今の時代と非常にうまくシンクロしているのかもしれない、と思いました。そう、今時代はデカダンなのかもしれない!
ただ、「無罪モラトリアム」とか「絶叫ソルフェージュ」とか「下克上エクスタシー」とか、椎名林檎の持つ不思議な単語感覚が20歳の女性としてはいまいちスマートには感じられないのですが。
詩もさることながら、やはり彼女の特徴はその歌い方にあります。
激しくシャウトし、息遣いや泣きがバリバリに入っている。そして、そのボーカルを際立たせるために、エコーやリバーブがほとんど使われずその代わりにコンプレッサーがかなり強力にかかっています。コンプをかけることにより、本来なら小音量にしかならない息遣いや喉の鳴りまでがリアルに録音されるのです。さらに、過激なことに「幸福論」という曲の中ではボーカルにディストーションがかかっています。この曲の最後はほとんど悲鳴に近いのですが、これにディストーションがかかっているから、ほとんどエレキギターのチョーキングのような音色になっています。
こういったサウンド上での芸の細かさ、声色の使い分け(かなり頻繁にある巻き舌にはちょっと笑える)、など自己演出に非常にこだわるのがわかります。どんな曲を歌っても同じにしか聞こえないアーティストは結局、一発限りの斬新さしかない。でも、常に新しい自己演出を考えつづける頭のよさが彼女にはあります。それは、テレビで流れるビデオクリップにも感じられます。
意外だったのはソングライティングの才能。
これだけ過激な表現をするのに、曲自体は実にメロディアスで、むしろJ-POPの本流を行くような正統派メロディ。またドリカム顔負けのコードプログレッションも感じられ、音楽的才能にも恵まれているように思えます。
実際彼女の最近の曲は、かなり売れてきたことを意識してか、シュール度を少し低くし、キャッチーなメロディでちょっと売れ線を狙っているようにも受け取れます。少し過激な一面が逆に女性の共感を誘い、また現代の若者に共通する内面的な飢餓感をうまく刺激して、今後もかなり売れそうな予感です。
ただ30代のオヤジには、もうこんな過激な曲に熱く共感するのがしんどくて、ついついお耳直しに静かな曲を聞きたくなってしまうのですけど。
◇戻る◇

 キリスト教徒でない人でも、聖書という書物が世界中で読まれ、また多くの芸術、文化の源になっていることは誰でも知っていることでしょう。ところが一度その中をひも解いてみようとすると、なんとも読みにくい断片的な言葉の切れ切れが書いてあるだけで、背景がわからないと言葉の意味も全く分からないものです。
キリスト教徒でない人でも、聖書という書物が世界中で読まれ、また多くの芸術、文化の源になっていることは誰でも知っていることでしょう。ところが一度その中をひも解いてみようとすると、なんとも読みにくい断片的な言葉の切れ切れが書いてあるだけで、背景がわからないと言葉の意味も全く分からないものです。 この本の題名だけ聞いて、どのような内容の本を想像するでしょうか?
この本の題名だけ聞いて、どのような内容の本を想像するでしょうか? 私の身の回りの人も数多く関わっていたこの創作オペラの演奏会に行ってまいりました。
私の身の回りの人も数多く関わっていたこの創作オペラの演奏会に行ってまいりました。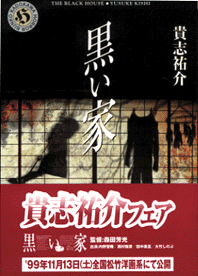 今、ちょうど映画でやっているんですね、この小説。
今、ちょうど映画でやっているんですね、この小説。 おっと、意外なものが、と思われた人も多いと思います。しかし、これは私にとって近年まれに見るヒットです。昔私がよく聴いていた筋肉少女帯とか戸川純とかと同じ系譜の、J-POP界の異端児とも言えるアーティストの登場なのです。
おっと、意外なものが、と思われた人も多いと思います。しかし、これは私にとって近年まれに見るヒットです。昔私がよく聴いていた筋肉少女帯とか戸川純とかと同じ系譜の、J-POP界の異端児とも言えるアーティストの登場なのです。