曲目:J.S.Bach「ヨハネ受難曲」
日時、場所:4月8日(水)19時開演、愛知県芸術劇場コンサートホールにて
Bach Collegium Japan(以下BCJ)「ヨハネ受難曲」名古屋公演に行ってまいりました。場所は愛知県芸術劇場コンサートホール。私はチケット代をけちってA席にしたのですが、行ってびっくり。私の席は舞台の上手側の真上。舞台を右側から覗き込むような場所でした。もちろん、最良の音響とはいえませんが、初めてのBCJの演奏会だし、間近で見れるのも悪くありません。まず最初にお断りですが、そのような座席だったため、近くにいるけど逆を向いている合唱団のベース陣、また舞台の前の方にいるエバンゲリスト、イエスのソロは必ずしもまともに聞けたとはいえませんので明確な評価はちょっとできないと思います。
BCJ、及びヨハネ受難曲について簡単に説明しましょう。
BCJとは鈴木雅明氏が主宰する日本におけるほとんど初めてのバロック専門プロアンサンブル集団です。名前の通りバッハ演奏が中心で、現在バッハの教会カンタータのCD録音が続けられています。彼らの演奏は、古楽器の使用、バロック的奏法など、最新の古楽シーンを見据えた知的なアプローチがされている点でも日本でユニークな存在といえるかもしれません。
さてヨハネ受難曲という曲ですが、これはヨハネによる福音書をベースとしたキリスト受難の物語が音楽によって語られるという曲です。合唱が中心となるコラール、ソリストが歌うアリア、エバンゲリスト(福音書記者)が歌うレシタティーボが交互に現れ、物語が進行されます。
さて、演奏ですが、感動にあふれた素晴らしいものだったと私は思いました。
ヨハネも実演で全曲聞いたのは初めてだったのですが、実に劇的な音楽で、バロック時代にすでにこのような音楽が作られていたとは信じられないほど。近代の管弦楽曲に劣らないほどのスペクタクル溢れる激しい音楽だと思いました。
そして、その劇性を鈴木雅明氏の指揮が的確に示していきます。横から指揮が見れたのは収穫。オーケストラの指揮者としての指揮のうまさという意味でなく、全身から溢れる表現意欲がオーラのように漂っているのです。また、レシタティーボでは自身がチェンバロを弾くのですが、今まで私の聞いた通奏低音のどれよりも表現が豊かで、通奏低音がここまでやっていいんだ、という新鮮な驚きがありました。なにしろ、鈴木雅明氏はかっこよかった。
そしてそんな思いは各団員にもしっかり浸透しています。器楽奏者も熱っぽく、特にソロになると全身を使って演奏していたのはとても印象的です。
ソリストでは、やはり米良さんの歌を聞けたのが一番のトピック。他のソリストも良かったですが、特に米良さんは表現たっぷりで良かったです。全員が黒一色の服装の中でも、茶髪でパーマがかった髪型とめがねルックはひときわ人目を引きます。なんだかちょっと太った原田真二みたいな感じ。しかし、低音のドスのある響きと高音の伸びやかな響きを使い分け、特にキリストの死に際のアリアでは情緒たっぷりの歌を聞かせてくれました。
合唱団は非常にハーモニーの美しい精度の高い合唱を聞かせてくれたと思います。ただ、合唱としての精度を求めるあまり、パートの音色は素晴らしく整っているものの、そのためにボリューム感や個人の表現力がやや損なわれている感じはありました。しかし、これもヨハネという音楽ゆえの注文であり、合唱のうまさとしてはかなりのものだったと思います。こういった合唱に求める部分にも従来にない発想が垣間見えます(特に日本のプロ合唱は酷いのが多いので)。
というわけで手放しの絶賛なのであります。私自身はまだ、バッハ演奏についてこうあるべきだなどと自分の哲学を持っているわけではないのですが、それでもこの日のBCJの演奏はバッハ演奏の中でも最良の部類に入るものだと確信できます。また、バッハ演奏というフィルターをかけるまでもなく、全く初めてバッハを聞いた人でもなにかしら感銘を与えることのできる演奏だったと思います。
最相葉月(さいしょうはづき)/小学館
 最相さんにより書かれたこの本「絶対音感」は、音楽関係者でない著者が「絶対音感」をめぐり、様々なインタビューをしたうえで、今まで誰も為し得なかった多面的なアプローチをしていることに価値があります。
最相さんにより書かれたこの本「絶対音感」は、音楽関係者でない著者が「絶対音感」をめぐり、様々なインタビューをしたうえで、今まで誰も為し得なかった多面的なアプローチをしていることに価値があります。
音楽関係者なら、絶対音感対相対音感、移動ド対固定ドといった論争をすぐ始めてしまうところですが、その際に、これほど広範囲な材料を持って議論できたかというとやはり否定せざるを得ません。かくいう私も、実はこの本を読んで、目からうろこが落ちる思いでした。今では私が頑なな移動ド主義者であったことをちょっと恥じる思いさえあります。
この本は私が知らなかった多くのエピソードを語ってくれます。特に、絶対音感を持たないことを恥ずかしく思い、そのコンプレックスから絶対音感教育のプログラムが開発されたこと、またこのプログラムが日本において非常に効果をあげていること、戦時中には戦争に有用な能力として絶対音感教育が奨励されたこと、などです。
さらに、そのような音感が本当に教育可能なのか、脳科学の立場から取材するなど今まで思いもつかなかったようなアプローチがなされています。
もちろん、移動ド対固定ド論争にも触れ、これが専門教育は固定ド、義務教育は移動ドとする日本の音楽教育のねじれの問題であるという点にまで言及しています。
さらに驚くのは、この本が一般書であるのにも関わらず、音響物理学的な内容がためらわず書かれ、かなり専門的な知識を持っている人にも興味を持って読むことができるという点です。何ヘルツと何ヘルツでどんなうなりが出るとか、ピタゴラス音律の数学的な説明など、どのくらい分かる人がいるのかな、なんて余計な心配をしてしまいました。
もちろん、この本は「絶対音感」を単に技術的に説明する本ではないのです。その中から、ほんわり見えてくる音楽とは何か?といった究極の命題にまで接近しようとしているのです。
確かに、「絶対音感」を信仰するあまり、世界の異なるオケのチューニングに違和感を感じたり、どうしても平均律でしか弾けなくて外国人よりピッチが悪いと言われたりするのは悲劇でしょう。しかし、その中で、「絶対音感」を習得することと「音楽」を習得することの微妙な違いが浮き彫りにされ、ひいては我々日本人の芸術感にまで何らかの修正が必要なのではないか、と思わせるのです。
絶対音感の話だけにとどまらない一般的な真理が以下の言葉に集約されているように思えます。
「何かに依拠して絶対化すると楽で足場はしっかりします。しかし、それは絶対化の罠にとらわれる危険性があるのです...」
私たちはさまざまな現象を、一つの単位系の中に封じ込めるために絶対化させます。確かに多くの自然現象はこれによって解明されましたし、そういったアプローチを近代的とか知的なものだと考える習性がつけられてしまったように思います。ところが、こと人間の知覚に関しては、そのような絶対性ではなく相対性に支配されていることが明らかになるにつれ、このような発想そのものを見直す必要が出てきたように感ずるのです。特に、芸術においては、人間の持つ曖昧な感性に支えられているのであり、それを物理的に規定することは現代においてはまだ不可能です。そういったとき、私たちに出来ることはその曖昧な感性をひたすら磨くことだけなのです。それこそ、本当の芸術家の生きる道ではないかとあらためて感じたのです。
鈴木光司/新潮文庫
 リング、らせん、ループの3部作でおなじみの鈴木光司氏による小説。久しくこういったエンターテイメント小説を読んでいなかったのですが、あまりの面白さに読み始めてから一気に結末まで読んでしまいました。
リング、らせん、ループの3部作でおなじみの鈴木光司氏による小説。久しくこういったエンターテイメント小説を読んでいなかったのですが、あまりの面白さに読み始めてから一気に結末まで読んでしまいました。
氏の小説の面白さは、何といってもその卓抜なアイデアでしょう。また、個人の力ではどうしようもないような巨大な力、圧倒的な意志力、といったものを表現するのがとてもうまいのです。実は、最近「リング」も読んだのですが、同様なことを感じました。
エンターテイメント系の場合、あらすじ自体に意味があるので、ここで内容を書いてしまうとこれから読んでみたいと思う人にネタばれになってしまいますから、簡単な内容の紹介にとどめておきましょう。この小説は全体で3つの章から成っています。それぞれの章は全く別の時代の独立した話になっています。最初の章は、遠く一万年前のモンゴル砂漠に住む遊牧民族の闘争とそれに絡む恋愛のストーリー、第2章は大航海時代の太平洋に浮かぶ未開の島の人々と難破してそこにたどり着いた西洋人との出会いの話、そして最後の章はニューヨークのある作曲家と、離婚したばかりのある女性とのラブストーリー、そしてこの3つの話が様々なキーワードで結ばれ、そして最後に物語の発端となった二人の恋愛が一万年の時を超え、形を変えて成就するわけです。
なんと壮大な物語でしょう。読んだ後、まだフィクションの世界の中に自分がぽかんと置き去りにされたような浮遊感からしばらく離れることができませんでした。ああ、こんな面白い話があるんだなあ、ととても感動したのです。
ちなみにこの小説は1990年の日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞した作品で、決して新しいものではありませんが、久しくこういった小説を読んでいなかったので、全然今までこの本を知らなかったのでした。鈴木氏が浜松出身ということもあり、浜松の本屋で結構宣伝していて、それで初めて知ったのです。
ところで、実はこれに便乗した(?)CDが最近発売されました。その名も「楽園」。アーティストは加羽沢美濃、作曲家、ピアニスト。ところが、そのCDのプロデューサーがなんとこの鈴木光司氏ということで、思わず買ってしまったのです。音楽は久石譲っぽくきれいな音楽でまとめられていますが、硬派っぽいところもあって割とよかったです。ただ、同じ主題が延々繰り返され、楽想の発展があまりないところがちょっと退屈かもしれません。
旅のお供や、眠れない夜の一冊としてオススメ。たまには一万年のときを超えた壮大なファンタジーに酔ってみましょう。
辻仁成(つじひとなり)/新潮社
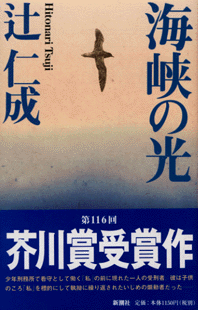 この前の談話で辻仁成の芥川賞受賞作を読んでいないと書いたのですが、あそこまで芥川賞について書いた手前、こりゃ読んでみなけりゃいけないと思い、早速入手しました。
この前の談話で辻仁成の芥川賞受賞作を読んでいないと書いたのですが、あそこまで芥川賞について書いた手前、こりゃ読んでみなけりゃいけないと思い、早速入手しました。
帯に派手に「芥川賞受賞作」と書かれており、いやがおうでも目に入ってきます。もともと、辻仁成を知ったのは、詩を探しているときに「応答願います」等が収められている詩集を手にしたときからで、小説はこの他に「パッサジオ」という本を読んだだけです。ちなみにこのパッサジオでは、ボイストレーナーが出てきたり、マタイ受難曲が歌われたりと、割と合唱好きに興味のありそうな内容だったのと、人の生と死の問題を扱っているにもかかわらず、ちょっととんでも系SFのようなノリがあってとても面白く読めたのでした。
だから、この本もそういった面白さを持っているのかな、と思っていたら、その期待は全く別の良い方向に裏切られたのでした。はっきり言って非常に硬派な小説です。それに内容がドタバタに陥らず、静かに進みながらも、人の心を抉る鋭さを持っていると感じました。
文章表現については、パッサジオで見られた書きなぐりのような勢いが少ない反面、含蓄のある言葉が丁寧に配置されており、純文学としての格調高さを感じさせます。
この話のおおまかなストーリーは、帯に書かれた言葉が端的に示しているでしょう。曰く「刑務所で看守として働く「私」の前に現れた一人の受刑者。彼は子供のころ「私」を標的にして執拗に繰り返されたいじめの扇動者だった---」
この言葉を単純に考えると「私」の復讐の話か、と思ってしまうのだけど、そうでは全くありません。この受刑者(花井という)に対する「私」の冷徹な観察を通して、過去の出来事を交錯させながら、「花井」の心理を何とか理解しようとする過程が書かれている、といったら良いでしょうか。
そして、私がこの本で感じたのは「花井」という特異なキャラクター作りの凄さです。しかしこれは一般社会の中では決して特異なキャラクターではなく、私たちの日常の中にも花井を感じさせる人たちはいます。こういう人間の描写のうまさが際立っているのです。花井を俗な言い方で表現しようと思ったら「二重人格」とでもなるのでしょうか。しかし、これはジキルとハイドのような独立した人格ではなくて、偽善的側面と本性の側面を冷たく使い分けるといった感じなのです。
この本では決して、この花井に対する主人公の非難が綴られているわけではないと思います。常に、花井との距離を測りながら、その存在を無視することが出来ず、主人公の中で一定の大きさを保っているのです。主人公はその鋭利な感覚で花井の偽善を小学生の頃から感じていたわけですが、自分以外のほとんどの人間は花井の正体を暴くことが出来ずにいます。もしかしたら、作者は花井の偽善性に気付くことの出来ない、ほとんどの人に対する非難をしているのかもしれません。そして、それは日本人のもっている特性と分かちがたいものだとしたら...
花井は下手をすると独裁者になれるような人格の持ち主でしょう。とにかく、人を口で動かすのがうまいのです。また、集団の中に共通のいじめ対象を作って、それによってその他の人の気持ちをまとめていくあたりはなんとも空恐ろしいものを感じます。しかし、この本では、結局花井は偽善に疲れ果て、刑務所の中に安住の地を求めます。そして、その「哀しさ」を描いた、とも言えます。
話は、単に花井と「私」の関係だけに留まらぬように、旧国鉄の青函連絡船で働いていたころの話、その昔の友人とのいさかい、夜の街で出会った女との関係、などを絡めることによって、一つのリアリティのある物語としての体裁を保っているように感じました。このあたり、もはや作家として十分な貫禄さえ感じさせます。
少々、暗い内容の話ではありますが、この小説、おすすめです。
anuna
Gimell PHCP-1939
 anunaは「アヌーナ」と読みます。このアイルランドの合唱団anunaのアルバムは、クラシックともポピュラーとも言えない、不思議な音響空間を醸し出しています。
anunaは「アヌーナ」と読みます。このアイルランドの合唱団anunaのアルバムは、クラシックともポピュラーとも言えない、不思議な音響空間を醸し出しています。
確かに人の声で作られている音楽ですから、もちろん合唱と言えるわけですが、実際に音楽を聴くと電気的に音場が処理されていますし、かなり積極的にエフェクトやミキシングを利用していますから、そういう意味ではポピュラー的なサウンド作りとも言えるでしょう。
クラシック側の人に言わせると、そういうのは邪道ということになるのかもしれませんが、このアルバムでは非常に上品なアンビエントを作り出すのに成功しています。むしろ、合唱という枠にとらわれていないために、一般の人が聴いても十分に気持ちいい音楽であると思いますし、逆に、我々合唱を楽しんでいる人が、こういったアプローチでもっともっと合唱音楽の聞き手を増やしていくべきだとも思うのです。
音楽は、アイルランドの中世の音楽がベースになっており、グレゴリアンチャントのような旋法的なメロディと、現代的な和音がきれいにマッチしています。また、それらの曲と交互に配列されるように現代的な曲(いわゆるポピュラー風)も入っていて、それらの繊細で美しいハーモニーがまた大きな魅力の一つです。編曲、作曲のほとんどはこの合唱団のディレクターでもあるマイケル・マッグリン(Michael
McGlynn)によって行われています。
全体的にアカペラが中心ですが、中にはギターやフルートなどの楽器も入ります。しかし、あくまでメインは歌です。ソプラノの可憐な歌声はほんとに涙もの。
もし、この音楽をジャンルに分けるとしたら、ヒーリングミュージックということになってしまうのでしょうか。特に最近、こういったヒーリングものというが流行っているそうで、このCDもそういった時流に乗って多くの人に聞かれるようになるかもしれません。なんだか、毎日の疲れを音楽で癒そうっていう発想も情けないものがありますが、私個人で言えば、こういう音楽で幻想的な気持ちに浸るのは結構好きです。声高に自分を主張する音楽よりも、やはり私はこういうほうが好みなのかも。
◇戻る◇

 最相さんにより書かれたこの本「絶対音感」は、音楽関係者でない著者が「絶対音感」をめぐり、様々なインタビューをしたうえで、今まで誰も為し得なかった多面的なアプローチをしていることに価値があります。
最相さんにより書かれたこの本「絶対音感」は、音楽関係者でない著者が「絶対音感」をめぐり、様々なインタビューをしたうえで、今まで誰も為し得なかった多面的なアプローチをしていることに価値があります。 リング、らせん、ループの3部作でおなじみの鈴木光司氏による小説。久しくこういったエンターテイメント小説を読んでいなかったのですが、あまりの面白さに読み始めてから一気に結末まで読んでしまいました。
リング、らせん、ループの3部作でおなじみの鈴木光司氏による小説。久しくこういったエンターテイメント小説を読んでいなかったのですが、あまりの面白さに読み始めてから一気に結末まで読んでしまいました。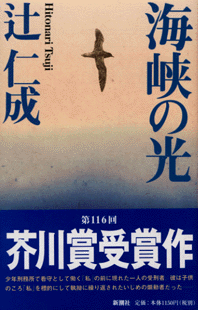 この前の談話で辻仁成の芥川賞受賞作を読んでいないと書いたのですが、あそこまで芥川賞について書いた手前、こりゃ読んでみなけりゃいけないと思い、早速入手しました。
この前の談話で辻仁成の芥川賞受賞作を読んでいないと書いたのですが、あそこまで芥川賞について書いた手前、こりゃ読んでみなけりゃいけないと思い、早速入手しました。 anunaは「アヌーナ」と読みます。このアイルランドの合唱団anunaのアルバムは、クラシックともポピュラーとも言えない、不思議な音響空間を醸し出しています。
anunaは「アヌーナ」と読みます。このアイルランドの合唱団anunaのアルバムは、クラシックともポピュラーとも言えない、不思議な音響空間を醸し出しています。